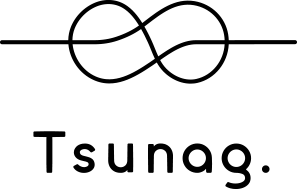冬期灌水田んぼ、稲刈りまで終わって一区切り。
2024年収穫後の秋冬から始めた“冬期灌水”。
大芦での実践1年目、無事に収穫までたどりつけました。
そして生き物の力をお借りしてのお米づくりを目指してたまたまではありますが
今日2025年12月2日、コウノトリと思われる鳥が冬水田んぼに飛来しました。
見つけてくれたのは移住者仲間のくまさん。

生き物が増えていく田んぼを目指してやってみて、
生き物でも目に見えるものと目に見えにくいものがあり
結果から言うとコウノトリが来てくれたことは論より証拠でとても勇気づけられました。
(なんかたまたまだとしても来る理由が何かあるはず)

そして収量は反あたり4.5俵ほど、無肥料。美味しさもあり満足。
前半田植え後の水や草の管理、後半の除草、そしてケガなど課題もありつつ、
「この条件なら悪くない」と言えるチャレンジだったと思います。
なるべく工数を抑えつつも自分たちが安全で美味しい、周辺自然環境にも配慮したお米づくりを確立していくために実験を続けていきます。
できたお米は田んぼに関わってもらった人にも届けていきます。

▽冬期灌水とは?
めちゃくちゃ簡単に言うと冬の間も、田んぼに水を張り続ける農法です。
目的は主にこの3つ:
- 春の草の発芽を抑える(酸素・光を遮断)
- 微生物環境を安定させる、生き物を増やす
- 春の代掻きを軽減できる
“なるべく耕さないで育てる環境を整える”という、再生型農業的なアプローチにも近い技術。でも始めて何年かは耕す必要もあるし、よく観察してノウハウを蓄積していきたい。
▽やってみて分かったこと
【◎良かった点】
- 草の発生はある程度抑えられたところもあった
- しかしまったく抑えられなかったところが多かったので、環境配慮の除草剤も1-2回使用(タイミング遅かった)
- 初期の生育が安定、場所によって分けつがよかった稲も。1株40‐50本ほど
- 代掻き時にすでに水が張っているのでトラクター作業の省力化
- 冬~春、カモなど野鳥が田んぼにいることが多かった
- 米がうまかった
- 12月2日にコウノトリが来た、翌日もいた
【▲反省点】
- 観察を良くする、藻が発生したのでその対応と活かし方
- 除草剤は使ったがホタルイ、コナギが繁茂した
- 代掻きの回数を増やす必要性あり(草対策として)
- 下記写真の右側はホタルイやコナギなどあります。

今回チャレンジできているのは、以下の条件があるからでしょうか。
- 冬でも水が取りやすい湧き水が上流にある
- 個別に水位調整できる
- 他の農家に迷惑がかからない、小言を言われない
- 地域の水利ルールに反していない
- 周囲に理解がある、もしくは誰もいないなど
これらが揃ってない田んぼでは、信頼関係が不足しているとやらない方が安全。
▽雑感
- “自然に優しい”ではなく、“条件が整ってるからやれる”、こともある
- 草を生やさないのではなく、“草との付き合い方を変える”
- 次年度はもっと収量あげたい、最低反5俵とか
- フクヒカリは実験的に種を継いで10ー20年でこの環境に適応するか試してみたい
- 品種は変えてみてGW田植えにするか、8月末~9月5日までに刈り取り出来たらかなり良い
- 稲が倒れないように、病気にならないように
- 稼働時間は改めて数えてみるが2.5反で100時間いくかなぁ?もうちょっと少ないか
来年は草対策のために代掻きの回数を増やす方向で検討。棚田でも圃場整備が入った1反前後の田んぼなら条件が合えば冬季潅水栽培での道筋が見えるはず。
参考までに 冬期灌水田んぼの雑草対策スケジュール(美作市上山地区@大芦・田植え5月中旬)
> 秋〜冬(稲刈り後〜翌年2月)
・稲刈り直後から 常時湛水(5〜7cm)をキープ
・藁は表面に残す
> 早春(3〜4月)
攪拌(軽代掻き)を2回
1回目:3月末
2回目:4月中旬
※この間も水は絶対に抜かない。
>田植え前(5月上旬〜中旬)
・スターレーション代掻き
・5月上旬に代掻き → 1週間待つ
・その間に草が発芽 → 田面を再度軽く攪拌して埋没
・その後に本代掻き → 田植え(5月中旬)
この「一度草を生やして潰す」工程が最大のポイント。
>田植え直後(5月中下旬〜6月)
・深水管理(5〜7cm)を2〜3週間維持
→ コナギやホタルイは光不足で抑制。
・初期除草剤か余裕があればチェーン除草機 or 手押し除草機を1回以上
→ 初期の草を対応。
>中後期(6月下旬〜7月)
・手取り除草は最低限
→ 中期以降の発生は、稲の葉が茂ればある程度抑えられる。
→ なるべく「草に種を落とさせない」
・このサイクルを2〜3年続け、コナギ・ホタルイを減少させたい。
>稲刈り(8月末か9月はじめ)
>そしてまたコウノトリが飛来してくれるお米づくりを継続する。
大芦高原でのお米づくりに関して一年後までの稲作スケジュールと目標がなんとなく決まった。
「来年もコウノトリが来てくれる田んぼとする」
「コウノトリが居着いてしまう田んぼづくり」
Tsunag合同会社では次の春から共に動ける地域おこし協力隊を募集しております。
詳しくはこちらの記事をご覧ください。
→「ここでは“暮らし”がキャリアになる」 ― 岡山県美作市・上山の“狩猟×棚田”地域おこし協力隊(企業研修型)募集 ―